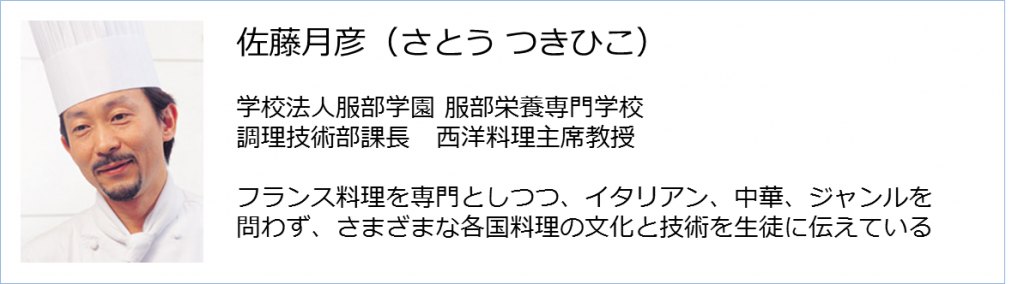はじめに
私の専門はフランス料理で、普段は西洋料理を学生たちに教えています。その経験を踏まえてなるべくわかりやすく、フレンチに日本のだしに相当するものはあるのか、あるとすれば、日本との違いは何かについて、述べてみたいと思います。
まず、かつお節や昆布のだしとまったく同じようなものは、基本的にフレンチにはありません。しかし、昨今はフランス人も、日本で日本料理を学んで帰国します。ですから、フランスでもかつお節や昆布が随分使われるようになっています。
いつ、フランスにだしの概念が伝わったのか、明確なことはわかりませんが、私の経験から言って、日本文化が大好きなフランス人は多いです。昨今のフランスにおける日本の漫画人気もそうですが、フランス人は日本の文化を取り入れることに抵抗がないと感じます。1970年代にヌーベル・キュイジーヌが始まったころ、フランスの三ツ星シェフが日本を訪れました。そのころから少しずつ日本料理のだしの技術などが広まり始めたのではないかと思います。例えば、当時、服部学園が日本に招聘した奇才、アラン・サンドランス氏は、最初に「だし」を使い始めたフランス人シェフの一人だと思います。
フレンチのサラサラ化
ここからは簡単にフランス料理の歴史に触れながら、日本のだしに近いものを見ていきましょう。
フランス料理のみならず、すべての西洋料理のルーツはイタリア料理にあります。16世紀、イタリアのメディチ家のカトリーヌが、フランスに嫁いだことをはじめ、結婚をきっかけに、イタリアの宮廷料理がヨーロッパ各地に広がり、それぞれの土地で発展していきました。フランス料理はこれらの中の一つです。
おもしろいのは、イタリア料理が入ってくるまで、ヨーロッパの人々は手で食べていたということです。フランスをはじめ、イタリアを除くヨーロッパには、ナイフやフォーク、スプーンという道具の概念そのものがありませんでした。では、人々はどのように食事をしていたのでしょうか。答えは単純、手で食べていたのです。
手で食べるならば、液体よりも固体のほうが食べやすいのは当然です。では、液体はどのようにして食べていたのかというと、固体であるパンに吸収させて食べていました。最近はあまり見かけませんが、昔ながらのグラタンの上にはチーズだけではなくパン粉がかかっているのをご存じでしょうか。あれも、手で食べやすい固形に近づけるためでした。
パンに付けて液体を食べるにしても、サラサラの液体よりも、どろっとした液体のほうが付けやすいですね。ですから、フランス料理のソースは濃いのです。
日本でよく知られているソースにドゥミグラスソースがありますが、このソースは、焼いて焦げ色を付けた肉、骨、野菜を水から6~8時間煮ていきます。さらに煮ることも珍しくなく、昔ながらの洋食店では、「当店は3日煮込んで作ります」という宣伝文句を見かけます。このように膨大な時間と労力をかけてドゥミグラスソースを作る時代がありました。しかし、スピード化が著しい現代にお店もそこまで手間をかけていられません。しかも、しつこいくらい濃厚な味わいも現代のニーズには合わなくなってきました。昔、貧しい時代に貴重だったものはカロリーや栄養価の高い食べ物で、それはすなわちバターや卵でした。しかし、現代では高カロリーの食べ物が敬遠されるようになったのです。
これらの要因から、1970年代後半になると、フランスではドゥミグラスソースは消えていき、ドゥミグラスソースほどの時間はかからないフォン・ド・ヴォーが主流となっていきます。同様に、バターや小麦粉でとろみを付けたルーを使ったソースも減り、サラサラとしたソースが増えていきました。ルーの代わりに水溶き片栗粉を使うようになったのもこのころからです。
この話は、先程のグラタンをイメージしていただければわかりやすいと思います。昔は、日本でもグラタンを注文すると、パン粉がたくさんかかっていて焼き色が付いていました。チーズの下のベシャメル・ソースはとろみが強くて、お皿と一緒に出されるのはフォークだけでした。ところが今はチーズを乗せただけで焼いてあるグラタンが主流で、昔に比べればベシャメル・ソースはサラサラしています。そのため、フォークと一緒にスプーンを出してくれるお店がほとんどです。こうした動きに呼応するように、サラサラとした日本のだしもフランスに受け入れられるようになったのではないでしょうか。
フォンとは何か?
フレンチで、あえて日本のだしに近いものを挙げるとすれば、フォンでしょう。フォンを日本語に訳すとすれば、だし汁になります。フォンにバターと小麦粉を加えてとろみを付けたものがルーで、フォンやルーにさまざまな手を加えたのがソースです。
フォン・ド・ヴォーを例にしてみましょう。フォンはだし、ヴォーは仔牛のことで、つまり、フォン・ド・ヴォーとは、仔牛のだし汁のことです。材料は新鮮な仔牛の肉と骨、同じく新鮮な野菜です。材料が新鮮であることが大切です。まず、材料を焼いて焦げ色を付けたら、それを水から長時間かけて煮出します。そのとき、丁寧にアクを取ること、沸騰後にはミジョテ(静かに微笑むの意で、軽い沸騰状態を保つ程度の火加減)を維持することが大切です。
ミジョテの維持が大切なのには、明確な理由があります。ボコボコと沸騰させると、泡が破裂したときに出る音波によって、水と油が乳化して白く濁ってしまうのです(この性質を利用して作るのが、九州ラーメンで知られる白濁した豚骨スープです)。
前述の通り、このフォン・ド・ヴォーが70年代後半にフランス全土で広まり、そのころフランスで修業していた日本人が80年代に帰国して、日本でどんどんフォン・ド・ヴォーを使い始めました。
余談ですが、日本でフォン・ド・ヴォーを作るには問題が一つありました。当時、日本では仔牛の入手が難しかったのです。ヨーロッパではチーズ作りに不可欠なレンネットを取るために、仔牛をと畜します。そのため仔牛の肉と骨の入手は容易でしたが、日本は牛の頭数がヨーロッパに比べても少なく、仔牛も存在しないに等しい状態でした。成長した牛でフォンを作ればいいと思うかもしれませんが、牛は臭いが強いので、フォンには不向きです。臭いのない仔牛で作るからこそ、クセのないフォンとなり、それがさまざまな料理のベースとなり得るのです。そこで、日本のシェフたちは、仔牛に代わる入手しやすいクセのない鶏で、フォン・ド・ヴォライユを作ったものです。
話をフランスに戻します。仔牛は仔牛で、鹿は鹿で、仔羊は仔羊で、それぞれフォンを作っていたら時間がかかって大変です。そこで、基本的には、フォン・ド・ヴォーに他の動物の骨と肉を加えて別の風味を出します。おもしろいのは、鹿の骨を焼いてフォン・ド・ヴォーに入れても「鹿のフォン・ド・ヴォー」とは言いません。鹿の香りになってしまうので、「鹿のフォン」と言います。「ヴォー」は消えてしまうのです。仔羊を入れたら仔羊のフォンになります。先程、仔牛は臭いがないと言いましたが、つまり、仔牛の風味が加えた動物に勝ってしまうことはないのです。
フォン・ド・ヴォーのようにクセがなく基本のフォンとして使うものには、このほかにフォン・ド・ヴォライユとフュメ・ド・ポワソン(魚のだし汁)があります。この三つが基本になります(図1参照)。
宮廷から家庭へ
ここまで見てきたドゥミグラスソースにしても、フォン・ド・ヴォーにしても膨大な時間と大量の材料が必要です。キロ単位の材料を大きな鍋でじっくりと時間をかけて煮出していきます。
なぜ、フランス料理は、ここまで時間と労力をかけるのでしょうか。それはフランス料理がもともと宮廷料理だからです。宮廷料理人には、仕える主人に対して「これだけ頑張りました」と言える部分が必要でした。それで一生懸命大量の材料を時間をかけて煮込んだのです。
しかし、こんなに手間がかかってしまっては、家庭料理には向きません。少ない材料で短い時間で作れる家庭料理的な発想で生まれただし汁として、フランス料理にはジュがあります。英語でジュースのことです。材料は基本的にフォンと同じですが、抽出する時間が短いので、仔牛よりも骨が小さい仔羊、鶏、鹿などを使います。また、抽出する時間が短いので、フォンに比べて香りとゼラチン質が少ないという特徴があります。
ジュを作る場合、材料を焼くのではなく、油で炒めるのが一般的です。炒めた後の油は臭いも味も良くないのでざるにあけて捨てます。そして炒めた材料をフォンと同様、水から煮て沸騰したらミジョテで2時間前後(材料による)かけて抽出していきます。
ブイヨンとは何か?
もう一つ、フレンチでだしに近いものとして、ブイヨンとコンソメに触れましょう。フォンと同様、材料の新鮮さが重要です。
丸鶏や牛すね肉に玉ねぎやセロリなどの野菜をゆでていきます。フォンと違って材料に肉類の骨は入りません。代わりにブイヨンには牛すね肉のゼラチン質が溶け出すので、フォンよりもまったりとした濃いだし汁になるわけです。また、ゼラチン質による輝きも出ます。材料を煮て肉がやわらかくなったらお皿に取ってマスタードと塩を付けて食べるのがポトフです。鍋に残った汁がブイヨンになります。
このブイヨンに今度は牛すね肉のひき肉、細かく切った玉ねぎ、人参、セロリ、卵白を加えてさらに煮出したものがコンソメになります。ブイヨンやコンソメを作る際にもミジョテとアク取りが大切です。
フレンチのスープをポタージュといいますが、ポタージュの分類にはクレールとリエがあります。クレールはクリアの意味で透明なスープです。リエはリエゾン=繋ぐ、という意味で、とろみの付いたスープのことです。もうおわかりのように、ブイヨンもコンソメもポタージュ・クレールに分類されます。
ブイヨンからコンソメを作り、そのコンソメを冷ましてからさらに肉を加えて煮出すコンソメ・ドゥーブルもあります。このようにフレンチにはどんどん足し算をして旨みを濃縮していく発想があります。これも宮廷料理ならではの手間です。
比較で知る日本のだし
ここまでフォンとジュ、ブイヨンとコンソメについて説明してきました。ここで、もう一度まとめて整理しましょう。
先程も述べましたが、フォンは大量の材料を膨大な時間をかけて煮出しただし汁です。それに対し、作り方はほとんど同じですが、ジュはフォンよりも少ない材料を使って、短時間で少量作ります。フォンもジュも基本的にはソースのベースになります。ジュの場合はそのまま煮つめてソースにすることもあります。
ブイヨンとコンソメも肉と野菜を煮出すという点ではフォンやジュと同じですが、骨が入りません。そして主にスープ(ポタージュ)になります。
ここまでを一度整理できたら、今度は日本のだしと比べてみましょう。
フレンチではフォンにしてもブイヨンにしても、大量の材料を膨大な時間をかけて煮出していきますが、これに対し、日本のだしでは、かつお節の場合は沸騰したところに入れてすぐに火を止めますし、昆布の場合は沸騰する直前に火を止めて取り出したりします。つまり、日本のほうがだしを取る時間が圧倒的に短いのです。
もう一つ、大きな違いがあります。フレンチのだしは、材料が新鮮であることが重要です。これに対し、日本のだしはかつお節にしても昆布にしても、だしを取る前の段階、つまりかつお節作り、昆布作りに時間をかけます。
新鮮な材料を時間をかけて煮出していくフレンチのだし、時間をかけて旨みを高めたかつお節や昆布でさっとだしを取る日本、両者の違いは明確です。
だしの保存性もフランスと日本は違います。取りたて、10分後、1時間後、翌日でだしを飲み比べたことはありますか? 日本のだしは1時間もすれば味が劣化します。一方、長時間かけて抽出したフォンやブイヨンはしっかりと保存すれば2週間は保ちます。ただし、抽出する時間の短いジュは日本のだしと同様、すぐに使うのが基本です。
作る分量にも違いがあります。日本のだしは基本的に使う分量しか作りません。これはジュに近いですね。
また、日本人には、かつおだしが好きな人もいれば、昆布だしが好きな人もいて、かつおと昆布の合わせだしが好きな人もいます。麺つゆなどを買うときには、かつおだしか昆布だしか、迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところがフランス人が、仔牛のだしか、鶏のだしか、というように、何ベースのフォンかで、料理を選ぶことはあまりないと思います。
中華だしを少々
簡単に中華のだしにも触れておきましょう。中華のだしもフレンチと同じく、長い時間をかけて材料を煮ていきます。図2をご覧になればおわかりの通り、中国には、さまざまな材料で取った湯(タン)があるのが特徴かと思います。大きく分けて葷湯(フンタン)(動物性、魚介類の湯)、素湯(スゥタン)(植物性主体の湯)に分かれます。このほかに、清湯(チンタン)(湯が澄んでいる)、白湯(パイタン)(濁っている)の区別があります。
フレンチのフォンと同様、中華のだしは、日本のだしに比べて時間をかけて抽出するのが特徴です。フォンと同様、時間をかけて取った湯は、日本のだしに比べれば保ちは良いと思います。一方で、ハムや干貝柱、干アワビ、干エビなどの加工品をだしの材料とするところは、かつお節や昆布と近いのではないかと思います。
こうして国ごとにだしの材料や取り方を比較してみると、その国の料理の歴史が浮かび上がってきて、大変興味深いものです。それぞれの特性を理解しながら、だしを使い分けていくと、料理も一層楽しくなるに違いありません。
【参考文献】
・『基礎と献立 フランス料理編』学校法人服部学園 服部栄養専門学校 編(服部栄養料理研究会 2006年)
・『基礎フランス料理教本』ロジェ・プリュイレール、ロジェ・ラルマン著(柴田書店 1991年)